馬をミライに繋げるために必要なこと。馬に関わるお金について🐎
- Loveuma.

- 2025年8月1日
- 読了時間: 5分

引退馬支援の事業家として業界を牽引する、株式会社 TCC Japan・代表取締役の山本 高之氏が、
「馬のミライ」をつくるための、考えや想いをお伝えします。
皆さん、こんにちは!
株式会社 TCC Japan 代表取締役の山本 高之です。
過去回では主にこれまでの歩みをお話ししてきましたが、今回からは私が「馬のミライをつくること」について考えていることや、今後の構想についてお伝えしていきたいと思います。
さて今日は、「馬に関わるお金」についてのお話です。
現役の競走馬には必ず馬主(オーナー)が存在し、馬主が預託料を支払うことで馬を預かる厩舎(調教師)があり、馬の世話や調教をするスタッフ(厩務員や調教助手)の仕事が成り立っています。
また競馬で稼ぐ賞金もそれぞれの関係者に決められた割合で配分されており、賞金は言わずもがな馬券売上が原資となっています。
その競馬自体を施行するのが、中央競馬であれば日本中央競馬会(JRA)です。
ここ数年は馬券売上が年々上がっているため、賞金もサラブレッドの生産頭数も増えてきています。
しかし、その分 引退していく競走馬の頭数も増えているのが現状です。

いざ競走馬としての役割を果たせなくなり登録を抹消されると、瞬く間に 1円も稼ぐことができない状況に陥ります。
馬主としても、競馬に出走して賞金を稼ぐことができなくなると預託料を払い続けることが困難になり、馬を手放すことがほとんどです。
もちろん中には、そのまま馬を持ち続ける方や、そこまでは難しくても次の居場所を探して譲渡される方もいらっしゃいます。

つまり競走馬として登録抹消されると、馬が自分で稼ぐことができなくなるだけでなく、同時に飼料代などを捻出する原資が無くなるケースがほとんどなのです。
それでも毎日の飼料や敷料代、預託料、世話をするスタッフの人件費、怪我をして引退したなら治療費など、生きていくための経費は待ったなしで必要となります。
その馬たちのミライをつくること、それがいかに大変なことか想像していただけますでしょうか。
特に大きな怪我で引退した馬なら、なおさらです。
治療費などの費用を掛けても、半年後や一年後、お金を生み出す仕事ができるかは分かりません。
そんな馬たちを、どうやってミライに繋げるか。

まず避けては通れない問題が「お金」です。
そこに、真正面から向き合わなければなりません。
1頭の馬を所有して乗馬クラブや牧場に預けようとすると、預託料として年間 150万円程度は必要になります。
またそれにプラスして、装蹄費や治療費なども必要です。
競走馬を引退してから馬生を全うするまで 20年間あるとすると、一昔前では一軒家が建つぐらいのお金が必要となります。
1頭でもそれだけ掛かることを考えると、とても一人で引退競走馬の支援活動を行うことは無理があります。
まずぶつかる問題がお金をどう工面するか、どうやって集めるか、どうやって稼ぐかです。
「乗馬としてセカンドキャリアで活躍する、(左)プロジェクト(右)ドリームドルチェ」
「トレーニングを重ねながら、ふれあいでも人気の(左)サトノパシュート(右)マジックカーペット」
私たちが支援活動を始めた当初は、「そんな活動は手弁当でやれ」といったような、お金のことで色々と言われることが何度かありました。
日本では人も動物も一緒で、福祉活動に対して「儲けてはいけない」「手弁当で」「ボランティアで」というような風潮が少なからずあり、子ども達への福祉事業も同時に行っている私としては、その風潮を変えていきたいとチャレンジしてきた部分でもあります。
今では、この部分においては理解が進んできたように思います。

近年少しずつ、「引退競走馬支援の分野に参加したい」「自分で活動したい」ということで、私のところに相談に来られるケースも増えてきました。
共通して課題としてあげられるのが、まさにお金の問題です。
想いだけは誰にも負けない自信があるけれど、お金をどう工面していいか分からない。
ただそれは、それだけ馬を本気でなんとかしたい人という人たちが増えてきた証拠です。
本気でない人はお金に向き合う必要がないので、前述したようなことが言えるのだと思います。
本当に難しい問題ですが、大切なことはまず真剣に向き合うこと。
お金から目を背けることは簡単ですが、それでは何も達成できずに想いだけで終わってしまいます。
そして、さらに大事なこと。
それは、皆さまからの大切なご支援や、馬とスタッフと共に死に物狂いで稼いだ大切なお金を何に使うか、どのように使うかです。

次回は、その大切なお金をどういったことに使ってきたかについてお話ししたいと思います。
Profile
山本 高之(やまもとたかゆき)
株式会社TCC Japan 代表取締役
1980年、滋賀県栗東市生まれ。
大学卒業後、コンサルタント会社での勤務を経て、2006年に東京でITベンチャーを起業。
東日本大震災を機に地域の重要性を感じ、出身地である「馬のまち 栗東」で馬に関わる事業を起こすことを決意。
2015年9月、地域の障がいをもった子どもたちのためのホースセラピー施設「PONY KIDS」を開所。
2019年5月、引退競走馬をセカンドキャリアにつなげ、馬と人の福祉活動を行う拠点「TCC セラピーパーク」、2023年には東京表参道に「BafunYasai TCC CAFE」をオープン。
2025年4月には、滋賀県高島市のメタセコイア並木沿いにTCC初の観光養老牧場 「メタセコイアと馬の森」をグランドオープンし、 引退競走馬を事業で生かす様々な取り組みを展開している。
文:山本 高之(株式会社 TCC Japan 代表取締役)
編集:椎葉 権成・近藤 将太
著作:Creem Pan


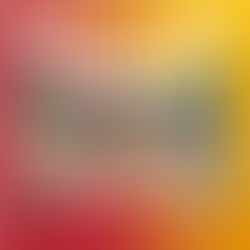















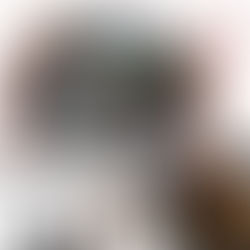















コメント