競走馬引退後、ミライに繋ぐための 3つの課題🐎💭
- Loveuma.

- 2025年7月4日
- 読了時間: 4分

引退馬支援の事業家として業界を牽引する、株式会社 TCC Japan・代表取締役の山本 高之氏が、
「馬のミライ」をつくるための、考えや想いをお伝えします。
皆さん、こんにちは!
株式会社 TCC Japan 代表取締役の山本 高之です。
これまで、活動の歩みを時系列にご紹介してきました。
前回からの続きのお話ですが、2014年から2015年にかけて、本格的に引退競走馬の支援プロジェクトを立ち上げるための準備に取り掛かりました。
「全国各地の様々な馬施設を視察させていただきました」
1頭でも多くの馬を次のキャリアに繋げていくには、どうすればいいか。
全国各地の視察や様々な方との意見交換の中で、主に 3つの課題解決に取り組む必要があると考えました。
1.競馬引退後の不透明な流通
競走馬として登録を抹消されると、馬主も調教師もなるべく早くその馬を退厩させるという選択をせざるを得なくなります。
馬主としては、もうレースに出走できない馬を預けておくと、日々の預託料が発生します。また調教師からすれば、競走馬として走れない馬を数に限りのある馬房に置いておくわけにはいきません。
このような理由から、次の行き先を探したり決める時間の余裕がないまま退厩を余儀なくされ、その後の流通が不透明になる原因となります。
馬名が変わってどこかの乗馬クラブでセカンドキャリアを送っていたとしても、競馬ファンや競馬関係者との繋がりはほぼ途切れることになります。
2.各乗馬施設が各々で行っている乗用馬への転用
今は普通に使われるようになった「リトレーニング」という言葉。実は私がこのプロジェクトの骨子をつくったときにアメリカから引っ張ってきた言葉でして、それまでは転用や再調教という言葉が使われていました。
それまでも、競馬関係者との繋がりや流通ルートを持っていた乗馬クラブでは、当たり前に競走馬から乗用馬への転用調教を行っていました。
ただ乗用馬への転用は、技術力の問題、怪我のリスク、調教期間中の経済的・人員的負担など様々な課題も多く、実際に取り組むことの出来る所が限られている状況でした。
3.競馬ファン(関係者含む)の関わり
先ほどの不透明な流通の部分でも触れましたが、応援していた馬や携わっていた馬を引退後も追いかけたい・会いたいと思っても、引退直後から行方が分からなくなることがほとんどでした。担当の調教助手や厩務員さんですら、知らないことがほとんどです。
競馬引退後を追いかけては行けないという暗黙のルールの中、半ば諦めていた競馬ファンや競馬関係者の方も多いかと思います。
その馬が競走馬として頑張ってきたドラマやストーリーが途切れてしまい、また一から乗用馬として生きていく環境しかありませんでした。
このような大きな課題に対し、どのように取り組んでいけばいいのか。
それまでの当たり前に変化を起こし、受容してもらい協力を得るためには、どのように物事を運んでいけばいいのか。
次回は、課題解決に向けた取り組み、「サンクスホースプロジェクト」の骨子についてお話をしたいと思います。
どうぞお楽しみに。

Profile
山本 高之(やまもとたかゆき)
株式会社TCC Japan 代表取締役
1980年、滋賀県栗東市生まれ。
大学卒業後、コンサルタント会社での勤務を経て、2006年に東京でITベンチャーを起業。
東日本大震災を機に地域の重要性を感じ、出身地である「馬のまち 栗東」で馬に関わる事業を起こすことを決意。
2015年9月、地域の障がいをもった子どもたちのためのホースセラピー施設「PONY KIDS」を開所。
2019年5月、引退競走馬をセカンドキャリアにつなげ、馬と人の福祉活動を行う拠点「TCC セラピーパーク」、2023年には東京表参道に「BafunYasai TCC CAFE」をオープン。
2025年4月には、滋賀県高島市のメタセコイア並木沿いにTCC初の観光養老牧場 「メタセコイアと馬の森」をグランドオープンし、 引退競走馬を事業で生かす様々な取り組みを展開している。
文:山本 高之(株式会社 TCC Japan 代表取締役)
編集:椎葉 権成・近藤 将太
著作:Creem Pan














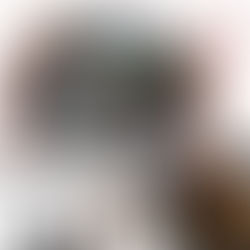





























コメント