「全員から好かれなくていい! 引退馬ビジネスの風雲児」岩﨑崇文(Yogiboヴェルサイユリゾートファーム) 1/2
- 2022年8月8日
- 読了時間: 8分
更新日:1月7日

北海道沙流郡日高町に引退馬支援に新たな風を吹き込む一つの牧場がある。
Yogiboヴェルサイユリゾートファーム。
クラウドファンディングや企業とのタイアップなど、これまで行われてきた引退馬支援とは違った角度から展開されるこの牧場の活動は、2015年から同牧場の代表を務める岩﨑崇文さんの若い感性によって開拓されてきた。今回は牧場経営における一つの「事業」として行っている引退馬支援について、岩﨑さんの思いを聞いた。

写真:Yogiboヴェルサイユリゾートファーム 代表・岩﨑崇文さん(本人提供)
大手企業の内定を蹴り、牧場を受け継ぐ
1993年に東京で生まれ、幼少期にはロサンゼルスでの生活も経験した岩﨑さんは小学校3〜4年生の頃に兵庫県明石市で乗馬を始めたことで馬と関わりを持つようになる。

写真:幼少期の岩﨑さん(本人提供)
最初はポニーから始まった乗馬だったが、特に怖いという感情はなく、「大きいな」と思ったのをよく覚えているという。高校入学を機に関西を離れ、東京にやって来た岩﨑さんに大きな転機が訪れたのは大学卒業が迫った2015年のことだった。
「ちょうどそのタイミングで父が亡くなって。でも『牧場は残して欲しい』というのが遺言だったので、そのまま北海道に来ました」

写真:家族写真。左は父の義勝さん・右下が母の美由紀さん(本人提供)
就職が内定していた大手企業に断りを入れて、牧場を引き継ぐことを決めた(岩﨑さん)。勿論、人生の大きな分岐点だったが、当時は漠然と「東京の人混みから離れたい」と考えていたのも相まって、全くプレッシャーには感じなかったという。

写真:東関東ホースパークにて、岩﨑さん、所有馬のカリブロ、スタッフさん(本人提供)
常用馬と競走馬の違いに戸惑いながらも、先代の時から携わってくれているスタッフに教わって現場の仕事を覚えていった。牧場を引き継いだ当時は繁殖牝馬と1歳馬の他に育成馬も預かっていたが、多額の借金を抱えていたこともあって育成部門を廃止し、繁殖だけで牧場を立て直すことを決めた。幸いにも引き継いですぐに活躍馬が出たことで、繁殖牝馬を預託してくれるオーナーも増え、牧場の経営自体は好転した。
牧場を引き継いで1年が経ち、牧場も岩﨑さん自身にも少しばかりのゆとりができてきた頃、北海道に来た当初にスタッフから聞かされた言葉を思い出したという。
「乗馬をやっていた時に引退馬に乗っていたこともあったので、こっちに来た時に繁殖生活を終えた馬たちがどうなるのかをスタッフに聞いたら、肥育業者が買って持っていってくれるんだよと。その話を聞いた時に、『何かちょっと違うんじゃないかな』と思いまして」
育成部門を廃止したことで管理している馬が減り、空きが出ていた馬房と放牧地を利用してせめて牧場に貢献してくれた馬たちだけでも預かることができないかと養老部門を立ち上げた。馬術や乗馬の世界では馬の最後まで面倒を見るという例は決して少なくない。岩﨑さんの周りにも同じような思いを持つ友人たちがいた。
名馬・ローズキングダムとの出会い
「友人からも『そういうことをやってくれるなら、預けたい』と言われていたので、ひっそりとはじめたんです」
最初はひっそりと始まった養老馬の預け入れだったが、牧場としての大きな転機が訪れたのは2018年、ブリーダーズ・スタリオン・ステーションからローズキングダムを受け入れたことだった。2010年のジャパンカップなど重賞5勝を挙げたローズキングダムは2013年からブリーダーズ・スタリオン・ステーションで種牡馬として活動を行なっていたが、2018年に馬房内で頭を強く打つ事故を起こし、身体に麻痺が残ってしまったことで種牡馬としての活動は困難になった。東京から来て牧場を引き継いだ岩﨑さんを以前から気にかけてくれていたというブリーダーズクラブには、養老部門を始めたということは伝えていた。
「牧場同士の距離も10分くらいだったので、何かあった時もすぐ駆けつけることが出来るからぜひ引き取って欲しいというのが始まりでした」

写真:タニノギムレットと岩﨑さん(本人提供)
ローズキングダムを受け入れたことで、養老部門が一気に注目を受けることになり、見学希望の問い合わせも急増した。養老部門があるということが認知されるようになったその一方で新たな問題も生まれた。生産が主だった当時、多くの見学者を受け入れるには体制が整っていなかった上、預託してくれているオーナーの馬に迷惑をかけるわけにもいかなかった。
「見学の問い合わせがすごかったです。その当時はそこまで引退馬に理解があるオーナーさんばかりではなく、一般的なオーナーさんの馬を預かっていたこともあって、さすがにちょっとまずいよね、と。そこで近くで牧場を探したらたまたまここが空いていたんです」
預託馬のオーナーさんへの配慮と引退馬を見に来たいファンの受け入れを両立するために牧場を移動することを決めた。そうして今のYogiboヴェルサイユリゾートファームの原型が出来上がったのである。
現在、Yogiboヴェルサイユリゾートファームには9頭の引退馬と4頭の種牡馬、それから7頭の繁殖牝馬が繋養されている。養老牧場でありながら繁殖牝馬を繋養していることについては農業生産法人としての性質上、少頭数でも生産を行なっていないと農地が使えなくなるというリーガルな事情が関係している。その広大な敷地の中には厩舎や放牧地だけでなく、他の牧場ではなかなか見ることのない宿泊施設や放牧地を眺めながらブレンドコーヒーなどをいただけるカフェが併設されており、さながら日本ではないような非日常的な空間が広がっている。世の中に馬グッズが出回っていないことにも目をつけ、シルエットや馬名を入れた繋養馬のグッズ販売なども行われている。
異例の挑戦・クラウドファンディング
岩﨑さんは引退馬支援を牧場における一つの「事業」として捉え、しっかりとした収益を上げること目指して運営を行なっている。一般の牧場でも同じ収入源である預託馬の預託収入の他、前述した宿泊施設やカフェ、グッズの売上、サポーターという形の会員さんからの牧場や養老馬へのマンスリーサポート、そしてスポンサーとYogiboヴェルサイユリゾートファームには6つの収入源が存在していることになる。牧場全体の収益の割合は以下の通りだ。法人スポンサーが33%、預託料が26%で収益の6割弱を占める。さらにマンスリーサポートが17%、グッズ販売が15%、飲食が5%、宿泊が4%と続く。宿泊や飲食については、今後またコロナ禍のようなことが起こる可能性を考えればどう転ぶかはわからないと言え、マンスリーサポートも増減があって不安定なところがあるという。そのような中で、やはり預託料というのは安定した収入源であると言える。

資料:取材をもとに作成
「従業員と馬は、何かあった時でも必ず守っていかなければいけないですから」
そのためには一定数の割合で預託馬を確保しておく必要がある。それでもだからと言って、預託収入に頼り切った牧場運営ばかりでは引退馬支援の輪を広げることは難しいのではないかと岩﨑さんは言う。
「いつまでもオーナーさんに頼るわけではなく、自立できる牧場にしていかないと結局のところこういう牧場を増やしていくことができません。『こういう収益性があるよ』というのを見せていかないと銀行もお金を貸してくれないし、そういう事例をうちが作っていくことで他の方が参入しやすい環境が作っていけるんじゃないかなと思っています」
自らの立ち位置を「ベンチャーポジション」と例える岩﨑さん。満遍ない収入源がある環境を作ることで、何かが沈んでも別の何かで補える体制を作っていくことが大切だという。自身の東京でさまざまな人たちに出会い、色々な考え方や価値観を目の当たりにした経験と結びつけて、北海道の中だけで完結させるのではなく、外部からの意見を取り入れて「こうじゃないとダメ」「こうしないとダメ」だという論調をもっと柔軟に考える必要があるのではないかとも語る。しかし、やはり引退馬支援に収益性を見出すことについては当初、向かい風も強かったという。新しいものは一度否定されるのが世の常だとも言える。
「最初は『引退馬なんてやってどうするの』って言われましたし、『すぐ潰れるだろう』なんてことも言われていましたね」
牧場としては当時、異例とも言えるクラウドファンディングを駆使しての資金調達も行った。


「(周囲の目線は)何をやっているんだろうという感じでした。『クラウドファンディングって何?』というレベルだったので」
このクラウドファンディングは話題を呼び、その目標金額を達成する以上に大きな宣伝効果を生んだ。まさに若い世代だからこそ行うことができた取り組みの一つだったと言えるだろう。批判の声を受けながらも、岩﨑さんが迷ったりブレーキを踏んだりすることはなかった。批判も一つの意見として受け止めることは受け止め、割り切ることは割り切って「有名になった」と考えることにした。
「どうやっても批判的な意見は出てくるので…。みんなに気に入られる形ではなく、応援してくださる方を大切にしてどんどん発信していくというのが大切なんじゃないかなと考えています」





















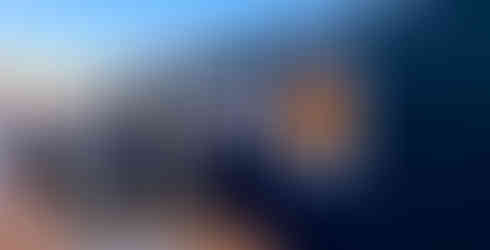



















「引退馬=金儲けしたらダメ」と思っている人は案外少ないのでは?
馬好きの誰が考えても、引退馬支援のためにお金が集まるのは大いに結構。賛否の分かれ目は、儲けたお金を「馬の福祉にどれだけ直接的に還元しているか?」という点だと思います。
ヴェルサイユリゾートファームのクラウドファンディングの例で言えば、第一回目は「損傷した老朽厩舎の建て替え」が目的で、当時はローズキングダムたちの他タイキシャトルやメイショウドトウもいたので初めから賛同者は多く、期間全体を通して満遍なく寄付が集まり、ごく自然な勢いで目標額を達成されたように記憶しています。
ところが第二回目は、寄せられた応援メッセージの温度が第一回目より低めだったことからもわかるように、初回に比べると出足が悪く、終盤で往年の有名ジョッキーの協力を仰いだり、限られた少数の人が多額の寄付をする等の努力があったりと、かなり苦労されていることが目立ちました。なぜか? 寄付を募る目的が「カフェの新設」だったからだと推測します。(個人の見解です)
馬たちが現に寝起きしている場所の改修でもなければ放牧地の整備でもない。たとえ「すべては馬のため」の遠大な事業計画の一環だったとしても、単体で見れば馬の福祉向上にどうしても必要な投資だとは考えにくい、完全に人間都合のプロジェクトだと受け取られたからではないでしょうか?(同上)
岩﨑さんのヴィジョンには賛同します。引退馬支援活動を成功した事業モデルとして確立したいという方向性は、絶対に間違っていないはず。ただ、焦りは禁物だと思う。その意味で、「古い厩舎を建て替えたい」からいきなり「新しいカフェを作ろう」へのステップアップは、ちょっと勇み足のようにも思えました。
成功に至るまでのペース配分はだいじです。ビジネスとしての成果を急ぎすぎず、本来の理想を共有してくれる賛同者を着実に増やしながら、ヴィジョン実現に向かって良いペースで進んで行ってください!